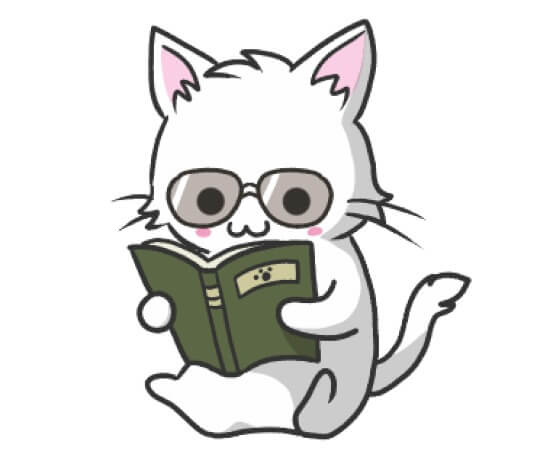サウナは、世界中で愛されている健康法の1つであり、長年にわたって様々な文化の中で発展してきました。サウナを楽しむためには、その文化や言葉に詳しくなることが大切です。
本記事では、週3でサウナに通っている筆者が、サウナを楽しむ上で必要不可欠なサウナ用語16選を紹介します。これらの用語を知ることで、サウナの世界をより深く理解し、さらにサウナを楽しめるでしょう。
サウナ用語16選!意味を紹介

サウナ用語16選をわかりやすく紹介します。
ロウリュ
ロウリュとは、サウナストーンに水をかけて蒸気を発生させることです。水に香りのよいオイルやハーブを加えることで、アロマ効果も楽しめます。フィンランド式サウナやロシアのバーニャなど、様々なサウナ文化で実践されています。
フィンランド式サウナ
フィンランド式サウナは、北欧地域で伝統的に実践されているサウナのスタイルです。特徴は以下の通りです。
- 木製のベンチがある
- サウナストーブに熱した石を載せる
- 石に水をかけて蒸気を発生させる
健康効果として、ストレス緩和や血流促進、肌の美容効果などが挙げられます。また、家族や友人と一緒に楽しむ社交的な側面も重要です。
バーニャ
バーニャは、ロシアを中心に広く実践されている伝統的なサウナのスタイルです。高温多湿の環境で、枝を使って体を叩くなどの独特の習慣があります。
サウナストーン
サウナストーンは、サウナ内で使用される加熱された石のことです。主な役割は以下の通りです。
- 熱を貯蔵する
- 水をかけることで蒸気を発生させる
- サウナ内の湿度と温度を調整する
サウナハット
サウナハットは、サウナで使用される帽子です。主な目的と特徴は以下の通りです。
- 頭部を高温から保護する
- 毛糸やフェルトなどの素材で作られる
- 汗を拭き取る
- 湿度を調節する
サウナタオル
サウナタオルは、サウナで使用する特別なタオルです。特徴は以下の通りです。
- 通常のバスタオルより大きい
- 薄く、吸水性が高い
- 汗や水分を拭き取るために使用する
- レンタルサービスが一般的
ヒートショックプロテイン
ヒートショックプロテインは、高温環境で細胞が産生するタンパク質です。以下のような効果があるとされています。
- 身体の防御機能を強化する
- 細胞の修復を促進する
- 老化防止に役立つ
サウナヨガ
サウナヨガは、サウナ内で行われるヨガのことです。主な特徴と効果は以下の通りです。
- 高温多湿環境で行う
- 身体をより深くリラックスさせる
- 柔軟性を高める
- 専門のインストラクターによる指導が一般的
オロポ
オロポは、オロナミンCとポカリスエットを組み合わせた飲み物です。サウナ後の水分補給に適しています。
サウナー
サウナーは、サウナを愛好する人たちを指す言葉です。主な特徴は以下の通りです。
- サウナ文化を愛する
- 健康やリラックス、ストレス解消を目的とする
- 様々な年齢層や職業の人が含まれる
- サウナー同士のコミュニティやイベントがある
ととのう
「ととのう」とは、サウナに入って身体を温めた後、身体を冷やしてリフレッシュするプロセスです。以下のような効果があるとされています。
- 血流を促進する
- 身体の循環を改善する
- 身体をリフレッシュする
サウナ飯(サ飯)
サウナ飯とは、サウナの後に食べる食事のことです。特徴は以下の通りです:
- 水分と栄養補給が目的
- 軽めの食事が好まれる
- リラックスした雰囲気で楽しむ
サ活
サ活は、「サウナ」と「活動」を合わせた言葉です。主な特徴は以下の通りです。
- サウナを中心とした健康的なライフスタイル
- サウナ関連のアクティビティやイベントに参加
- 身体的、精神的な健康を追求する
ドラクエ
サウナでの「ドラクエ」とは、複数人で一緒に行動することを指します。ただし、他の利用者への配慮が必要です。
あまみ
「あまみ」とは、サウナ入浴後に皮膚に現れる赤い斑点のことです。以下のような特徴があるようです。
- 腕や足などに現れる
- キリンやジラフのような柄
- 一般的には健康上の問題はない
- 自然に消えていく
羽衣
「羽衣」は、サウナ後の水風呂で感じる現象です。特徴は以下の通りです。
- 体の表面に薄い膜ができる感覚
- 冷たさを感じなくなる
サウナ用語のまとめ
本記事では、サウナに関連する代表的な用語16選を紹介しました。これらの用語を理解することで、サウナをより深く楽しめます。サウナは身体と心の健康に効果的とされ、世界中で愛されている健康法の1つです。ぜひサウナを通じて、健康的なライフスタイルを実践してみてください。